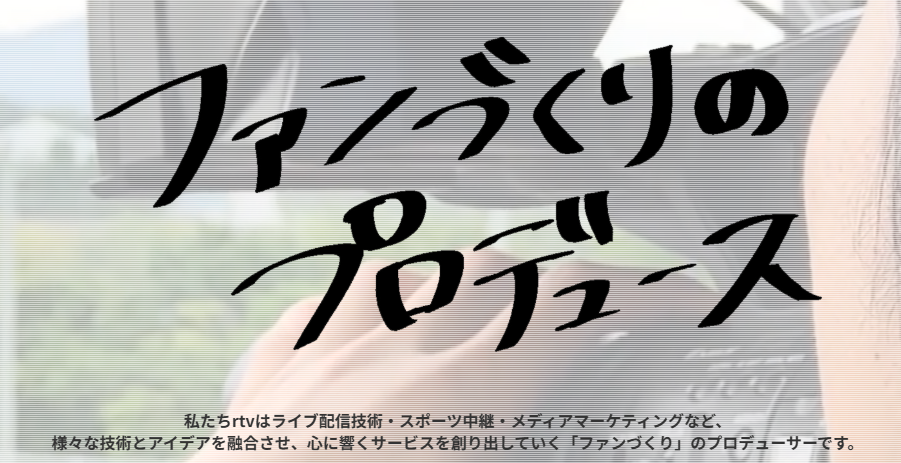【日本メディカルライン株式会社】「SDGsだけじゃ意味がない」SBT認定取得企業が挑む本気の脱炭素経営


- 事業内容
- 医薬品デリバリーサービス・医薬品物流センター管理・次世代除菌システム/基礎化粧品の販売
- 企業サイト
- https://j-m-l.jp/index.html
日本メディカルライン株式会社は医薬品のデリバリーサービスを主軸とする企業です。病院や調剤薬局へ高品質な配送を提供し、地域医療を支えています。
創業当初よりSDGsの取り組みを続け、ファストカーボン導入後の2024年11月には中小企業版SBT認定を取得しました。
宮城県内でSBTを取得した数少ない企業の1つとして、業界をリードしながら環境負荷の低減に積極的に取り組んでいます。その背景について、日本メディカルライン株式会社の庄子様にお話を伺いました。
(取材日:2025年2月27日 インタビュアー:ディエスジャパン広報)
INTERVIEW LIST
日本メディカルライン株式会社の事業内容
庄子様:日本メディカルライン株式会社は、2016年の設立以来、医薬品のデリバリーサービスを提供している企業です。
メーカーや県内の医薬品卸から在庫を預かり、調剤薬局や病院へ配送する独自の共配システムを採用して物流の効率化、そして安定した供給を支えています。
全国的にも珍しいこの仕組みは、宮城県内での認知も広がり、信頼を築いてきました。
また、物流業界で課題となる2025年問題に対しても、医薬品の卸・物流を通じて貢献しています。

日本メディカルライン様の倉庫
ファストカーボン導入について

ファストカーボン導入のきっかけ
庄子様:以前からSDGsを宣言して取り組み自体はしていましたが、言葉だけで実際の成果が伴っていなかったんです。
言ってしまえば、ほとんど自己満足に過ぎない部分が大きかったですね。
数字の見える化についても、なかなか具体的なアクションにつなげられていませんでした。
事業が拡大して所有する車両が増えていき、CO2の排出問題を真剣に考える必要性を感じていた矢先、ディエスジャパン様のお話を伺う機会がありました。
そして、すぐにファストカーボンの導入を決断し、2024年11月にSBT認定を取得することができました。
ファストカーボンの作業時間
庄子様:毎月入力作業をしていれば、10~15分で済みます。進捗も毎月確認できますし、電力会社などの設定を最初に行えば、後は数字を入力するだけなのでスムーズに進められています。
ディエスジャパンのサポートについて
庄子様:データの入力方法など、最初は分からないことも多くありましたが、その都度メールで質問をしました。毎回すぐに返信をいただけたので、問題なく導入を進められました。
SBT認定取得について
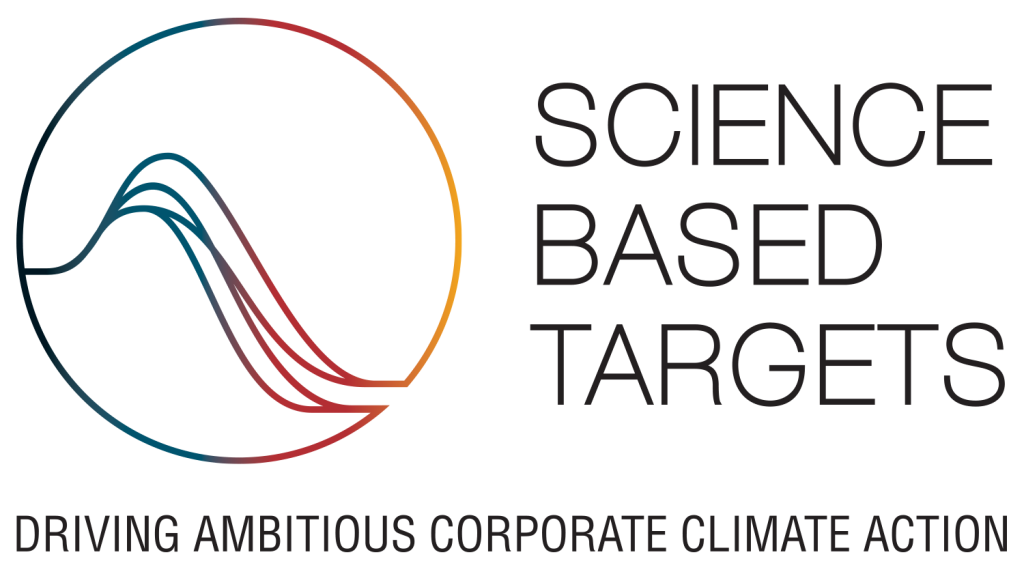
庄子様:SBT認定のマーク自体はどこかで見たことがあったのですが、ディエスジャパン様から詳しい説明を受けて初めて「そうだったんだ」と理解しました。
企業価値を高め、社会貢献活動に取り組むことが必要だと感じていたところに、タイミングよくお話をいただきました。
SBT認定の取得理由
庄子様:当社は、設立してまだ若い会社です。
付加価値を提供するためには、新しい取り組みが必要だと感じていました。
特に、大手企業ではすでにSCOPE3を進めているところも多く、その流れに乗り遅れないようにと考えたんです。
将来的に、そういった取り組みを求められる場面が増えるだろうという予感もあり、今のうちから先駆けて取り組もうと決めました。
SBT認定申請時の困った点や難しかった部分
庄子様:ディエスジャパン様に逐一分かりやすく説明していただいたので、特に困ったことはありませんでした。分からない点があればすぐにメールをしていたので、もしかすると他社よりもやりとりが多かったかもしれません。
早ければ当日に返信が来たり、メールではなく電話がかかってきたりと、毎回レスポンスが早くて助かりました。
取引先企業からの可視化の要請
庄子様:まだそのような依頼はありませんが、これから可能性はあると考えています。
現在、全国に拠点があり自社で配送を行っている大手製薬会社様が、仙台で当社の配送システムを試験的に利用しています。
このシステムでは、医薬品の温度管理とデジタルタコグラフ(※)の導入により、データが確実に取れる体制を整えています。
このシステムが全国に広がれば、環境への取り組みが問われることになるため、先んじてSBT認定を取得しようと決めました。
※デジタルタコグラフ:運転中の車両の速度や走行距離、運転時間などを記録・管理するデジタル機器
CO2可視化で見えた課題と変化

庄子様:細かいところまで数字を入力することで、CO2削減効果が高まるのは間違いありません。
以前は燃料費や電気料金だけを計算していたのですが、それでは不十分だと感じています。
例えば、社員一人ひとりの交通費なども今後はすべて算出していく予定です。
しばらくは以前よりも産出量が増えることが予想されますが、そこが本当のスタートだと捉えています。
そのため、社員の意見をしっかり取り入れながら、全社一丸となって取り組みを進めているところです。
ファストカーボンの導入、SBT認定取得で見えた課題
庄子様:当社では多くの車両を使用しているため、以前からエコドライブに取り組んできました。
急ブレーキや急発進を避け、車速は60キロ以下というルールを設けていましたが、燃料費の高騰に伴い、さらに車速を下げるべきか、安全性をどう確保するかが議論の焦点でした。
SBT認定を取得した後は、ルートの見直し等を通じて、生産性向上にも注力しようと検討しています。
CO2可視化で得た発見
庄子様:一番の驚きは、排出量が予想以上に多かったことです。
当社には軽バンが25台ほどありますが、比較的小さい車両なのに年間で約80トンのCO2を排出していると分かり、驚きました。
大きなトラックを使っている協力会社では、もっと膨大な排出量があると聞いていますので、まだ少ないほうだとは思います。
しかし燃料や電気料金だけでなく、従業員の移動にかかる部分も含めると、現時点での排出量はかなり増えてきていると認識しています。
2024年11月には排出量を集計して去年との差額を確認し、特に多く排出している部分を特定できました。その上で、課長やセンター長と協力して改善策を考えています。
改善案を具体化するのは簡単ではありませんが、互いにアイディアを出し合って進める過程をとても面白く感じています。
CO2可視化による経営改善における視点の変化
庄子様:物流では、業務効率化が売り上げに直結します。
利益率も重要ですが、CO2排出量削減とのバランスが大事です。売り上げを維持しつつ、どのくらい排出量を削減できるかが鍵になります。
システム上で解消できるのか、それともマンパワーが必要か、いろいろな課題が見えてくる中で、それらをトライアンドエラーで進めていくのが、ゲーム感覚で楽しくもあります。
ひたすら削減のみを追求し過ぎると現場が疲れてしまうので、現場の実感を大事にしながら、続けやすい形で進めていくことが重要だと思っています。
CO2可視化後の現場社員の反応

日本メディカルライン様では、女性スタッフが多数活躍しています
SDGsを始めた当初、社員たちは「社長はいったい何をしているんだろう?」という感じでしたが、まずは一人ひとりに取り組みを意識してもらうことからスタートしました。
パート従業員を含め、皆にドーナツ型のバッジを配りながら、これからこういった取り組みを進めていくんだという話をしたものです。
同じ形で、脱炭素経営についての意識も少しずつ社内に浸透していると感じています。
以前は燃料費、電気料金といった大まかな部分でしか見える化ができていませんでしたが、ファストカーボンを使えば社員一人ひとりの交通費といった細かい部分まで見える化できます。
いったんは算出量が増えると予想していますが、これは脱炭素経営に向けた第一歩だと考えており、現場と情報を共有しながら対話を重ねています。
今後の脱炭素経営に取り組みについて
庄子様:当社だけで取り組みを進めていても、おそらく3~4年後には限界が見えてくるのではないかと思っています。そのため、周りの企業の経営者たちと情報を共有し、協力していく体制づくりが必要です。
宮城県仙台市でSBTを取得している企業は、関東圏に本社がある企業を除けばごくわずかです。当社の取り組みを発信し続けることで、周囲の企業にも良い影響を与えたいと思っていますし、現時点でも少なからず実感ができています。
しかし、そのような草の根活動だけでは貢献度に限界があるのも事実です。私たちのような企業が増え、共に活動していくことが欠かせません。
そこで重要なのは、周りの企業が賛同できるような働き方や取り組みを示すことです。私たちの取り組みをより広く発信し、脱炭素経営に興味を持つ企業が少しずつ増えていけば良いなと思っています。
ファストカーボン導入メリット
庄子様:SBT認定後、名刺を一新してロゴマークを掲載しました。
そのマークをきっかけに、経営交流会などで「CO2の排出量、ちゃんと見える化できていますか?」と話す機会が増え、すでに数社にファストカーボンを紹介しています。
その際には、「今後、取引先からCO2排出量の提示を求められる可能性が高まる。
求められてから対応するのでは遅く、今のうちから取り組みを進めておくことが重要だ」と伝えています。
特にSBTの中小企業向け認定は年々ハードルが上がっているため、早めの申請が有利になる点も強調しています。
ファストカーボンを導入するなら、経営者自身が脱炭素への意識を持ち、主体的に取り組むことが大切です。
そうすることで継続しやすくなり、実際に私もそうでした。
今後も関心のある経営者に声をかけて、ディエスジャパン様へつなげていければと思っています。
ご協力いただき、ありがとうございました。