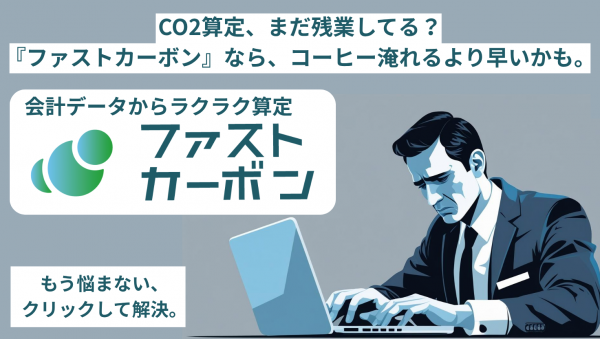生涯CO2排出量の算出義務化はいつから?建築業界の対応の変化

地球温暖化問題が深刻化する中、建築物の生涯CO2排出量の算出を義務化する制度を政府が検討しています。
2025年3月までに制度の具体的な内容を決め、2026年の通常国会に関連する法案を出す予定です。
今回は、そもそも「生涯CO2排出量」とは何か?
生涯CO2排出量の算出義務化はいつからになると予想されるか。
現在の建築業界の企業のCO2算出の取り組みと今後の対応の変化について解説します。
生涯CO2排出量とは?

「生涯CO2排出量」とは、ある製品や建物などが、原材料の調達から製造、使用、廃棄までの一生涯にわたって排出する二酸化炭素(CO2)の総量のことです。
具体的に、建築物で例えます。
- 原材料の調達: 鉄、コンクリート、木材などの材料を採掘したり、製造したりする際にCO2が発生。
- 材料の輸送: 原材料や製品の輸送過程の車両から排出。
- 建設: 材料を加工して建物を建てる過程(建設機械の使用、照明、溶接、加熱などの作業)からもCO2が出る。
- 使用: 建築物の運用段階でのエネルギー消費(暖房、冷房、照明など)、水消費、廃棄物発生などにCO2が発生。
- 解体: 建物を解体したり、廃棄物処理をする際にCO2が排出。
このように、建物の生涯を通じて様々な段階でCO2が排出されるため、その総量を「生涯CO2排出量」と呼んでいます。
生涯CO2排出量とは、建築物の建設から解体までのライフサイクル全体で排出されるCO2のことです。
生涯CO2排出量を測るメリット

建築物の生涯CO2排出量を測ることは、単に数値化することだけではありません。
建築と環境の関係性を理解し、持続可能な社会の実現に貢献するための重要な一歩です。
生涯CO2排出量を測るメリットを紹介します。
環境負荷の低減
省エネ設計や自然素材の活用など、CO2排出量を減らすための具体的な対策を講じることができます。
リサイクルや再利用を促進し、廃棄物量を減らすことができます。
建築の質の向上
環境性能が高い建物は、室内環境が良く、居住者の健康にも良い影響を与えます。
長寿命で耐久性のある建物になる傾向があります。
経済的なメリット
省エネ化により、ランニングコストを削減できます。
環境配慮型建築は、市場価値が高まる可能性があります。
生涯CO2排出量を減らすには?

建築物の生涯CO2排出量を減らすことは、地球環境の保全だけでなく、生活の質の向上にもつながる重要な取り組みです。
ここでは、建築物の生涯CO2排出量を減らすための具体的な方法とそのメリットについて解説します。
建築物の生涯CO2排出量を減らすための具体的な方法
省エネ設計の徹底
断熱性能の向上
外壁や窓の断熱性能を向上させることで、暖房・冷房に必要なエネルギーを大幅に削減できます。
自然エネルギーの活用:
太陽光発電、地熱発電など、再生可能エネルギーを積極的に導入することで、化石燃料の使用量を減らします。
設備の効率化
高効率な照明器具や空調設備を採用し、エネルギー消費量を抑制します。
再生可能エネルギーで作られた建材
太陽光発電で製造されたアルミや、水力発電で製造されたセメントなど、再生可能エネルギーで作られた建材を選ぶことで、製造過程でのCO2排出量を削減できます。
リサイクル材の活用
鉄鋼スラグやフライアッシュなど、産業廃棄物を再利用した建材を選ぶことで、新たな資源の採掘に伴うCO2排出量を削減できます。
生涯CO2排出量の算出義務化はいつから?
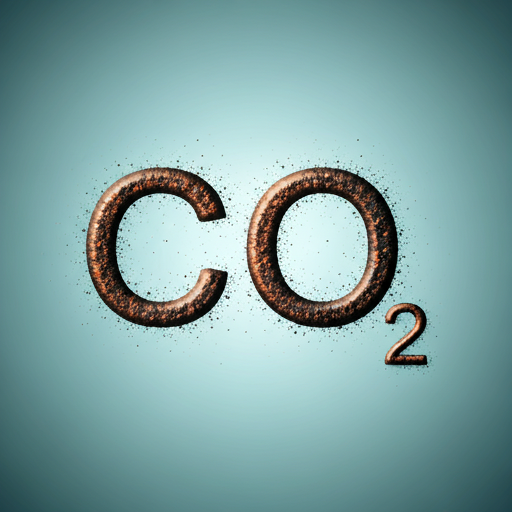
生涯CO2排出量の算出を義務化はいつからなのか、まだ具体的な日程は決まっていません。
義務化に関する法律は検討段階で、2025年3月までに制度の具体的な内容を決め、2026年の通常国会に関連する法案を出す予定です。
前例から、生涯CO2排出量の算出義務化を予想すると早ければ、2027年には法律が制定されると予想されます。
環境への取り組みに関する法律である「省エネルギー法」の原型となる法律は、1979年に制定されました。
2023年の省エネルギー法改正は、2022年中に国会に提出され、審議を経て、2023年4月1日に施行されました。
「省エネルギー法改正」の事例から考えると国会への提出の翌年に施行される可能性があります。
省エネルギー法とは?

エネルギーを効率的に使い、化石燃料への依存度を減らすことを目的とした法律です。
一定規模以上のエネルギーを使用する事業者は、エネルギーの使用状況や省エネへの取り組みについて、国に報告すること義務があります。
2023年の大規模改正
2023年4月に大幅な改正が行われ、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」へと名称が変更されました。
この改正では、非化石エネルギーへの転換を加速させるための新たな規定が加えられ、省エネルギー法の役割が大きく変化しました。
2023年の省エネルギー法改正は、2022年中に国会に提出され、審議を経て、2023年4月1日に施行されました。
現在の建築業界の企業のCO2算出についてと今後の対応の変化

建築業界の企業は、環境に配慮したさまざまな取り組みを行っています。
2025年1月現在、建築業界における企業のCO2算出は、企業規模や意識によって大きくばらつきが見られます。
大企業
サプライチェーン全体のCO2排出量を算出し、科学的根拠に基づいた目標設定と削減に向けた取り組みを進めている企業が増加。
国際的なイニシアチブへの参加や、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)への対応を進める動きも活発。
ESG投資の拡大に伴い、投資家からの要請を受けてCO2算出を強化するケースもある。
中小企業
多くの企業が自社のCO2排出量の算出ができていない状況です。
一部の企業で、自社の直接的な排出量(Scope1、Scope2)の算出は行っているものの、
サプライチェーン全体の排出量(Scope3)の算出は進んでいないケースが多い。
CO2算出にかかるコストや専門知識の不足が、取り組みの障壁となっている。
大企業ではCO2排出量の算定は進んでいますが、中小企業の多くはまだ何の取り組みも進めることができていません。
弊社が提供するファストカーボンでは、会計データのみで安価に簡単にCO2排出量の算定ができます。
属人化せず、1ヶ月分のCO2算定でも約10分程度と、通常業務の合間に作業できます。
詳しくはこちらをクリック
CO2算出義務化後の企業対応の変化
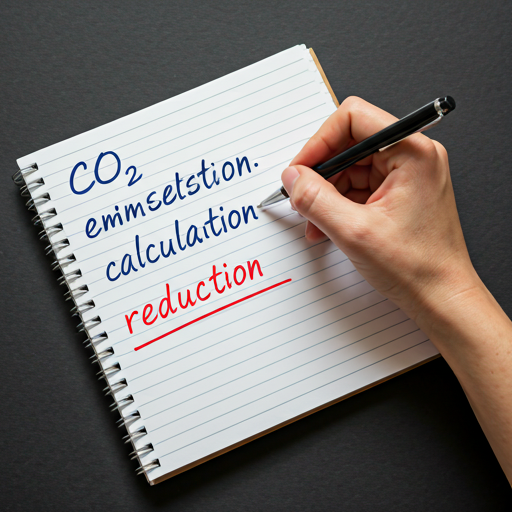
CO2算出が義務化されると、建築業界全体のCO2算出に関する状況は大きく変化すると予想されます。
中小企業への波及効果
義務化により、中小企業もCO2算出に取り組まなければなりません。
CO2排出量の透明性が高まり、消費者や投資家からの信頼獲得につながります。
CO2排出量の少ない資材や製品の調達、物流効率化など、サプライチェーン全体の脱炭素化が加速すると予想されます。
CO2算出義務化は、建築業界の大きな転換点となるでしょう。企業は、この変化を捉え、積極的に取り組むことで、持続可能な社会の実現に貢献していくことが期待されます。
建築物の生涯CO2排出量の算出義務化

この義務化により、建築物のCO2排出量の削減が促進され、地球温暖化問題の解決に貢献することが期待されています。
建築業界の企業は、生涯CO2排出量の算出義務化に対応するため、さまざまな取り組みを行っています。
- 省エネ性能の高い建物の設計・施工
- 再生可能エネルギーの活用
- CO2排出量の削減に貢献する材料の使用
- 従業員の環境教育
生涯CO2排出量の算出義務化はいつから?建築業界の対応の変化まとめ

生涯CO2排出量の算出義務化は、建築業界の企業にとって大きな課題です。
しかし、この義務化により、建築物のCO2排出量の削減が促進され、地球温暖化問題の解決に貢献することが期待されています。
生涯CO2排出量の算出義務化に関する法律は、現在検討中です。
具体的な制度設計は2025年3月までにまとめられ、翌年の国会に提出される予定です。
これまでの立法プロセスを踏まえると、早ければ2027年にはこの法律が施行される見込みです。
義務化される前に、CO2排出量の算定に取り組むことで、他社との差別化や義務化後もスムーズな対応が可能です。
弊社が提供しているCO2可視化ツールファストカーボンは、会計データのみでCO2を算定できるツールです。
スピーディーに導入でき、
作業負担を大幅に削減し、脱炭素経営を加速させましょう。詳細はこちらからご確認ください。
-
担当営業が詳しくご説明いたしますCONTACTお問い合わせ
- APPLICATIONお申し込み