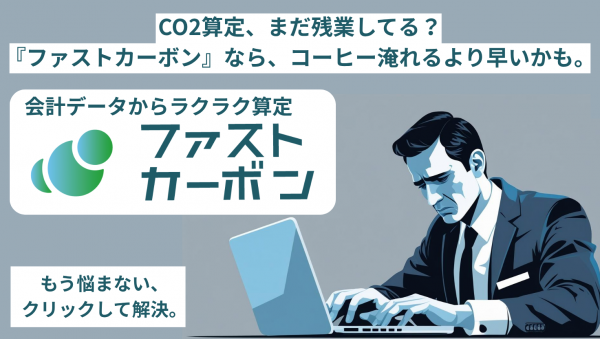カーボンオフセットは意味ない?その3つの理由と本当の問題点

企業のサステナビリティ活動が企業価値を左右する現代において、「カーボンオフセット」は脱炭素社会実現に向けた有効な選択肢の一つとして注目されています。
しかしその一方で、「カーボンオフセットは意味ないのでは?」といった懐疑的な声が聞かれるのも事実です。
「導入を検討しているが、社会的な批判リスクが気になる」「投資として本当に意味があるのか判断しかねている」企業の担当者の中には、このようなジレンマを抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、カーボンオフセットがなぜ批判を受けるのか、課題を3つの視点から解説します。
そして、これらの課題を乗り越え、カーボンオフセットを企業価値向上に繋げるための活用法と、具体的なアクションをお話しします。
カーボンオフセットの基本的な仕組み

カーボンオフセットとは、自社の事業活動などでどうしても削減しきれない温室効果ガス排出量を、他の場所での排出削減・吸収プロジェクトに投資することによって埋め合わせる(オフセットする)仕組みです。
具体的には、森林保全や再生可能エネルギー事業といったプロジェクトによって生み出された「カーボンクレジット」を企業や個人が購入することで、その排出量を相殺したと見なします。
この仕組みは、自社だけでは対応が難しい排出量(例えば、サプライチェーン全体での排出量であるScope3など)に対応する手段として、多くの企業に活用されています。
気候変動対策における資金循環という役割
カーボンオフセットの重要な意義の一つは、気候変動対策に必要な資金を世界中に循環させる機能です。
特に、資金や技術が不足している開発途上国で実施されるプロジェクトにとって、先進国の企業が購入するクレジットは貴重な活動資金となります。
質の高いプロジェクトは、CO2削減だけでなく、現地の雇用創出、生物多様性の保全、教育支援といった複合的な便益(コベネフィット)を生み出すことも少なくありません。
カーボンオフセットは、単なる排出量の穴埋めにとどまらず、地球規模の持続可能な発展に貢献するポテンシャルを秘めた仕組みです。
なぜ「意味ない」との声が上がるのか?乗り越えるべき3つの構造的課題

カーボンオフセットが持つ意義の一方で、その運用面には課題が存在します。
ここでは、各方面から「意味ない」と指摘される代表的な3つの構造的課題について解説します。
課題1:効果測定の難しさと透明性の確保
第一の課題は、プロジェクトによるCO2削減・吸収効果の測定と検証が極めて難しい点です。
例えば植林プロジェクトでは、植えた木が計画通りに成長し、長期にわたってCO2を吸収し続けるかを正確にモニタリングする必要があります。
しかし、その管理がずさんであったり、自然災害のリスクがあったりと、クレジットが示す数値通りの効果が発揮されないケースが指摘されています。
実際に2023年、世界最大手のクレジット認証機関の一つであるVerraが認証した森林保全クレジットの多くが効果を過大評価していた可能性を海外メディアが報じ、市場の信頼性を揺るがす事態となりました。
こうした実態の不透明さが、不信感を生む大きな要因となっています。
課題2:「追加性(additionality)」の証明という壁
第二に、カーボンクレジットの信頼性を担保する上で最も重要な概念である「追加性」の証明が難しいという課題です。
追加性とは、「もしクレジットによる収入がなかったとしても、そのプロジェクトは実施されていなかった」ということを意味します。
言い換えれば、クレジット収入があるからこそ、新たに追加で実現した削減・吸収活動でなければならない、ということです。
もし、もともと採算が取れていたり、法律で義務付けられていたりするプロジェクトがクレジットを発行していた場合、それを購入しても世界全体のCO2は減りません。
しかし、この追加性の有無を外部から厳密に判断することは困難であり、市場には追加性に疑いのあるクレジットが流通しているとの批判が絶えません。
課題3:本来の削減努力を阻害する「免罪符」化への懸念
第三の課題は、カーボンオフセットが、企業が本来最優先で取り組むべき自社の排出削減努力を遅らせる「免罪符」として機能してしまうリスクです。
事業構造の変革や省エネルギー技術への投資には多大なコストと時間がかかりますが、クレジット購入は比較的安価かつ容易に「環境に配慮している」という姿勢を示すことができます。
この手軽さから、企業が安易にオフセットに依存し、根本的な排出削減を怠ってしまうことは本末転倒です。
環境への貢献をアピールしながら、実際には排出削減が進まない「グリーンウォッシュ」の一環として利用されることへの強い懸念が、批判の根底にはあります。
クレジットの「質」が問われる時代へ

調べてみると、クレジットの価格はプロジェクトの内容や認証基準によって大きく異なります。
企業がコストのみを重視して安価で質の低いクレジットを購入することは、効果が期待できないだけでなく、企業の評判を損なうレピュテーションリスクに直結します。
これからの時代、企業には価格だけでなく、クレジットの「質」を見極める確かな目利きが求められます。
カーボンオフセットを「意味のある投資」にするために企業がすべきこと
数々の課題がある中で、企業はカーボンオフセットとどう向き合っていくべきでしょうか。
重要なのは、その位置づけを正しく理解し、戦略的に活用することです。
「削減階層」に基づいた正しい位置づけ
国際的に推奨されているアプローチに「削減階層」という考え方があります。
これは、①回避、②最小化、③再生・回復、そして最後の④オフセットという優先順位で気候変動対策に取り組むというものです。
つまり、まずは自社の事業活動に伴う排出を根本からなくす努力(①、②)を最優先し、それでもなお残ってしまう排出量に対して、初めてオフセット(④)を検討するという順序が鉄則です。
この原則に立ち、オフセットをあくまで補完的な最終手段と位置づけることが不可欠です。
信頼性の高いクレジットを選定する視点
クレジットを選定する際には、価格だけでなく、その「質」を担保するための多角的な視点が必要です。
例えば、Gold StandardやVerraといった国際的に認知された基準による認証を受けているか、前述した「追加性」が明確に証明されているか、CO2削減効果以外の生物多様性保全や地域貢献などがあるか、といった基準で評価することが重要になります。
第三者の専門家によるデューデリジェンスを行うことも有効な手段です。
ステークホルダーへの透明性高い情報開示
オフセットに取り組む際は、その内容を積極的に情報開示しましょう。
どの認証基準の、どの地域の、どのようなプロジェクトのクレジットを、どれだけ購入したのか。
そして、なぜそのプロジェクトを選定したのかという理由まで、統合報告書やウェブサイトで説明することが、ステークホルダーからの信頼獲得に繋がります。
オフセットは終わりでなく始まり。脱炭素社会への責任ある一歩として

「カーボンオフセットは意味ない」という批判は、その仕組みが持つ構造的課題と、一部の企業による不適切な利用に起因しています。
しかし、そのポテンシャルまで否定するのは早計です。
企業が取り組むべきは、まず自社の排出削減努力を徹底的に追求すること。
その上で、どうしても削減できない排出量を、透明性が高く社会貢献にも繋がる質の高いクレジットで埋め合わせることです。
カーボンオフセットは、脱炭素への取り組みの「終わり」を意味する免罪符ではありません。
自社の責任を自覚し、気候変動というグローバルな課題解決に貢献するための「始まり」の一歩として位置づける姿勢こそが、これからの企業に求められています。
-
担当営業が詳しくご説明いたしますCONTACTお問い合わせ
- APPLICATIONお申し込み